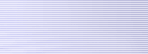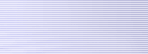|
 | 2003/7/22 |  |
何と言っても古紙流通が活発な主因は中国経済の目覚しい台頭で、需要の増加は世界中の製造業が生産拠点を中国にシフトし始めた10年前に遡ります。主に工業製品の梱包資材となる板紙消費量は昨年遂に前年対比200万㌧増にまで達しました。これは日本の増加量12年分に匹敵し、今や世界の古紙は中国に集まるとまで言われるほどの輸入量となっています。
当然、流通古紙がダブついていた日本などは、真っ先に調達のターゲットとなり、数年前あれだけ余っていた流通古紙の在庫は、瞬く間に姿を消すこととなるわけですが、安心していたのも束の間、止まるところを知らない需要の高まりは、遂に日本国内の製紙メーカーより原料を高く仕入れるという事態に発展します。
デフレが続き、古紙原料のコストアップが製品価格に転嫁出来ない国内の製紙メーカーは、あの手この手でこれを食い止めようとしてはいるものの、なにせ多少原料が高騰したところで、安い人件費がリカバリーして余りある中国が相手ですから、商社や企業もこぞって中国に古紙ヤードを開設して、輸出は沈静化しそうもありません。
中国が目覚しい経済発展を遂げたここ10年を、オフィスから排出される文書に置き換えて見ると、いずれの事業所でもリサイクルへの取り組みと、機密文書に関する情報管理の両面が向上したと言ってよいでしょう。特に機密文書については、一般古紙とは一線を引いた方法で処分されているわけですが、古紙市場での原料調達に苦戦を強いられる一部の製紙メーカーは、これらを市場価格に左右されない「オイシイ」原料調達市場として捉えはじめているようです。 |
前編で説明したDIP設備を導入している製紙メーカーでは、多少の不純物や禁忌品が混じっていても原料として使用できるように設備を発展させ、「段ボールごとの溶解で機密保持」という謳い文句でオフィス文書を原料調達のターゲットにしています。
機密文書の処理ということになれば、原料代がタダとか、逆に処理費用を頂戴できるのですから、経営的立場からすると確かにオイシイ話なのですが、企業から排出されるモノで機密を有するものは多様化しており、どのような状態で排出されるのか、文字通り「箱を開けるまではわからない」という実態からすると、生産の現場としてはそうも言っていられません。
これは機密文書専門でやっていればわかることなのですが、例えば製薬や化学メーカーから出されるものには、開発の過程で発生した、薬品等の化学物質が紛れ込んでいることも往々にしてあるのです。一応書類である前提だとしても、これらのものを何のチェックもせず生産ラインに投入することが、果たして継続して行えるものなのでしょうか?少なからず製紙業界の実情を知る私が、もし工場の品質管理責任者の立場になったとしたら即座にノーと言うでしょう。
良い紙製品を作るという製紙工場の基本業務に立って見ると、「営業や資材調達の連中は安い原料が欲しくて箱ごと溶解しますなどと言っているようだが、製品が売り物にならないような混入物が入っていて問題になったら、責任は俺達に来るんだ、現場では必ず中味をチェックして不純物は取り除いてからパルパーに投入するよう頼むよ。」となるのは必然です。
いくつかの製紙メーカーの担当者と話を交えた限り、彼らは生産する事が本分であり、作業員の教育も含め、機密情報を全責任を持って請け負う覚悟とか、体制整備も含め、万が一にも情報漏洩事故が起きてしまったら、賠償すべき補償で原料代の差益の数年分は吹っ飛んでしまうことを理解しているようには思えません。
依頼する側からすれば、機密文書が誰の目にも触れず溶解されるというフレーズに魅力を感じるこの方法も、工場側依頼側双方にとって、あまりに多くの問題を抱えている方法だと言わざるを得ないのです。 |
結城 寛
※写真は、ダンボールごと溶解することを特徴とする製紙工程から排出されたばかりの“スラッジ”と呼ばれる不純物。バインダーなどの事業系古紙には含まれているはずのものは見当たらない。
|
 |
 |
|

|